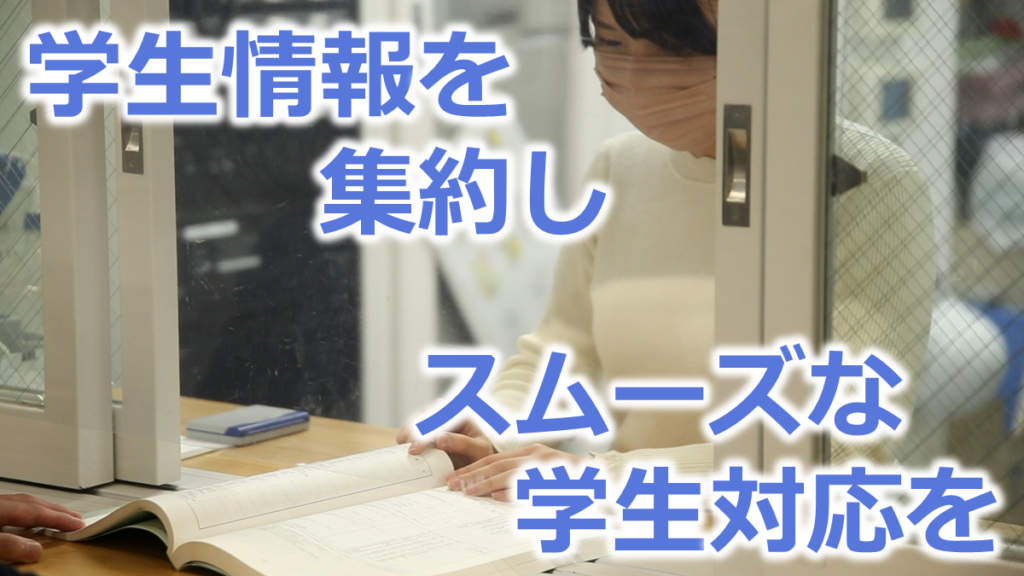宮城大学からの出向者・山﨑さんにインタビューしました
-大学DXアライアンスの運営を通じて-
東北大学業務DX推進プロジェクトでは、「DXを、ともに」をコンセプトに掲げ、組織の垣根を越えたさらなるDXの推進を目的として、「大学DXアライアンス」を発足しました。全国の大学や企業と連携し、各組織の知見やノウハウを共有することで、実践的なDXの取り組みを加速させています。
また、DXを担う職員のスキル向上や新たな視点の獲得を目的として、大学間の人的交流も活発に行っています。宮城大学から東北大学デジタル変革推進課に出向中の山﨑さんは、出向者としての新たな環境の中で、大学DXアライアンスの運営を担当。学外の多様な機関と関わる中で、DX推進の現場における課題や可能性を実感しながら、業務改善に取り組んでいます。
本記事では、山﨑さんに出向の経緯や業務内容、大学DXアライアンスの運営を通じて得た気づき、そして大学におけるDXの未来について伺いました。異なる環境での経験がどのような学びにつながるのか、そのリアルな声をぜひご覧ください。
プロフィール

山﨑 拓哉 さん
宮城大学 事務局 総務課所属。
現在、東北大学 情報部 デジタル変革推進課に出向し、業務のDX推進プロジェクト・メンバーとして大学DXアライアンスの運営を担当。
これまでの経歴を教えてください。
2020年に宮城大学に入職して、出向まで学務課に所属していました。主に学務管理システムの運用や教職員向け研修の企画、ラーニングコモンズの運営、授業アンケートの実施、事務業務のDX化に取り組んでいました。
それ以前は、医療機器メーカーに6年半勤務し、部品の製造工程の改善や新製品の生産ラインの立ち上げを担当しており、デジタルとは全く無縁の業務をしていました。
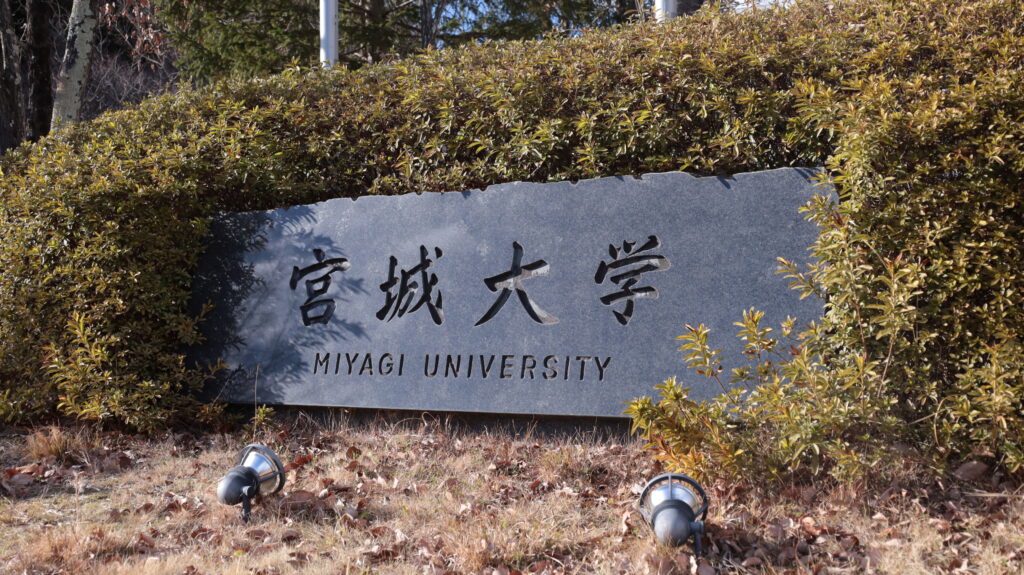
出向の経緯・きっかけ
2022年度から、学務課で事務業務のDX化を担当することとなり、MS365を活用して学生向けのポータルサイトを構築したり、メール対応やアンケート集計を自動化するなどの改善に取り組んでいました。
ちょうどその頃、東北地区業務DXチームのメンバー募集があり、DX推進について学び、他の職員と情報交換をしたいと思い応募しました。その後出向の話が持ち上がり、「これはもう内部に入り込んで体得するしかない」と思い、申し込みを決意しました。
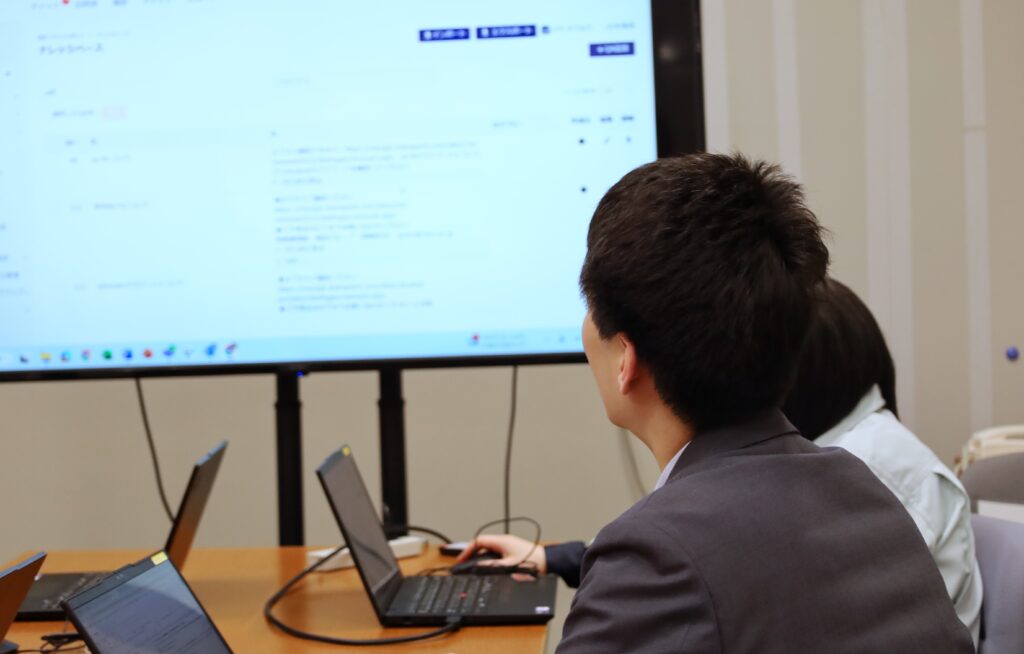
東北大学でのDXの活動では、どのようなことを行っていますか?
2024年4月から発足した「大学DXアライアンス」の運営メンバーとして、主に他機関からのアライアンス参加手続きの対応をしています。具体的には、学外からの問い合わせ対応と希望者向けの個別説明会、参加者向けのGoogleアカウントの作成や配付をしています。
参加手続きに関しては、Google Apps Scriptを活用して自働化していますが、より簡単にスムーズにできるよう、来年度実装に向けて新フローを構築中です。

東北大学業務のDX推進プロジェクトで活動する中で感じることは?
総長名で発表された「オンライン事務化宣言」の影響力は大きく、2022年に参加した当初から、全学部署横断で進められているのが印象的で、羨ましく感じた部分もありました。
大学DXアライアンスが発足した2024年からは、学内のみならず他大学や企業の方との交流がより活発化しました。外部からの客観的な意見を取り入れながら進められるようになったことは、2024年度の大きな成果だと感じています。

出向について
出向をして感じたことは?
情報部やDXチームに参加している職員のみなさん一人一人が課題意識を持って取り組まれているのが印象的でした。さらに、実施した取り組みを学内やチーム内で共有し、ウェブサイトで公表するまでの流れが確立されていて、スピード感があり素晴らしいと思いました。
また、テレワークにフレックスタイム、服装も含め、働き方のスタイルが自由に感じました。柔軟な働き方を支える環境や制度が整っていて、職員それぞれのワークライフバランスに合わせて働き方を選択できるのが魅力的だと思っています。
出向者としてだからこそ活躍できたと感じたことはありますか?
赴任してすぐに、大学DXアライアンスの参加受付フローの検討を行いました。学外出身だからこそ気づける視点があり、参加する側の立場で構築できたと思います。また、その後の他機関の方とのやり取りでも、同じ目線で話ができたことで、つながりを築きやすかったのではないかと感じています。
印象に残っていることはありますか?
プログラミングの知識がない中、先輩職員に時間を割いていただき、基礎から学びながらコードを書きました。何度もエラーに対応しながら試行錯誤を重ね、実際に動いたときは先輩職員と喜びを分かち合いました。単なる手法の一つかもしれませんが、大きな達成感があり、印象に残っています。
出向の経験で学んだことは?
これまでは、MS365など手元にあるツールを「どう活用するか」だけを考えていました。しかし、情報部に配属されてからは、ツールやシステムの使い方だけでなく、「なぜ必要なのか」「導入することで業務負担は減るのか」「属人化せずに運用できるのか」など、その先の影響まで考えるようになりました。


大学DXアライアンスの運営について
大学DXアライアンスの運営をしていて感じることは?
他機関の方々との手続きや問い合わせをきっかけにつながりが広がっていくのがとても嬉しいです。参加申込をされる方みなさまも、それぞれの所属機関で課題を抱え、自分事として捉えて対応策を模索されているのだと思い、その気持ちを私自身も忘れてはいけないなと思います。
大学DXアライアンスの魅力は?
東北大学でのDXの取り組みや使用しているツールの情報を収集できることに加え、各部局や他大学の事例を参考にできる点も魅力です。また、すぐに使えるツールをダウンロードして活用できるのも大きな利点です。
さらに、所属機関の事例を共有できるサイト(DX cabiNET.)や、他機関どうしで情報交換やコラムのやり取りができるコミュニティサイト(COLLABO TERRACE)もあり、お互い学び合いながら向上し合えるのが大きな魅力だと感じています。

他機関のDXに触れたことで得られた気づきは?
各機関によってDXの進め方やアプローチの手順、抱えている課題や背景は異なります。そんな中、どのようにDXを展開されたのかという裏話が聞けるので、自分や所属大学の進め方を俯瞰して見て、こういう進め方が有効だったのかと新たな気づきを得られました。意見交換をした機関の数だけ学びがあり、大きな収穫につながっています。

最後に

今後どのように大学のDXを発展させていきたいですか?
大学DXアライアンスのコンセプトにある「DXを、ともに」を続けていくことでしょうか。DXのように組織の変革を伴うような取り組みは、個人や所属機関では解決が難しいので、より多くの方が大学DXアライアンスに参加しやすくなるよう、環境を整えていきたいです。
DXをきっかけにしたコミュニケーションを通じて、それぞれの課題に合った情報交換ができる場にしていければと思います。
今後のビジョンや目標をお聞かせください。
東北大学のDXや大学DXアライアンスはもちろんですが、本務校である宮城大学の発展に向けても引き続き貢献していきたいと考えています。
出向期間が終わるのを待たずに、有益な情報は随時共有して、大学運営改善の一助になれば嬉しいです。